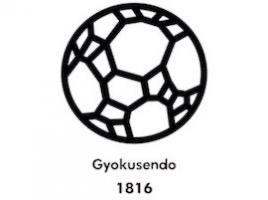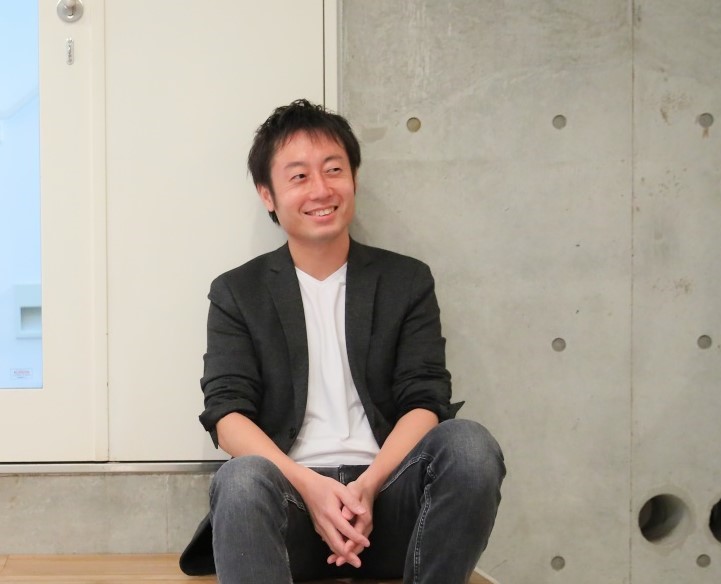写真提供:株式会社玉川堂、三条ものづくり学校
Text by ながいしほこ
時間的に、精神的に、余裕がなくなってきたなと感じるとき、私はコーヒーミルで豆を挽く。
深夜に、明け方に、ひとり、ガリガリと。
コーヒーミルの、ハンドルを回す感覚が好きだ。
豆の砕ける心地よい音と、ハンドルを握った手から伝わる振動、コーヒーの香り。
最後の一粒が砕けて、ハンドルがふわりと軽くなるあの瞬間。
一つひとつを味わって、丁寧にいれたコーヒーは格別においしい。
カップが空になる頃には、心のゆとりを取り戻す。
子どもの頃、コーヒー豆を挽くのが好きだった。
休日の朝、両親が飲むコーヒーをいれるために、姉とふたり、交代でハンドルを回した。
なんてことのない、日々のヒトカケラ。
でも振り返ってみるとあたたかで、幸福感に満ちた時間の記憶。
今でも実家に帰ると、同じコーヒーミルで豆を挽く。
昔は料理なんてしなかった父が朝食を作っている傍らで。
私がコーヒーミルを回し始めると、「やりたいー!」と嬉しそうに集まってくる子どもたち。
交代で楽しそうにハンドルを回すその姿が、幼い頃の自分とかぶる。
小さな手。力の入れ方が安定しないので、スムーズに回らないハンドル。
「10回ずつね」「いーち、にー、さーん…」「ちょっと見てみる?」「あけてみよう!」
なかなか終わらない作業。いいよ、待つよ。休日だしね。
楽しそうにコーヒーミルを回す子どもたちの向こう側に、私も両親も、きっと同じイメージを重ねて見ている。
40年近く前の、ある日の光景。
変わっていくもの、変わらないもの。
40年間、変わらずそこにあるコーヒーミルは、記憶と時間を繋ぐもの。
モノには、共に過ごしてきた日々の想いとストーリーが宿るのだと思う。
暮らしの中で使うものこそ、長く使える良いものを。丁寧に手入れをしながら、大切に使える好きなものを。
祖母や母から伝えられてきたその言葉の意味を、ここ数年で、やっと本当に理解できるようになった気がしている。
*
玉川堂の番頭、山田立さんのお話を伺うなかで「文化も産業も、生態系のようなものなのかもしれない」という考えが浮かんだ。
一つのモノが創り出され、使う人のもとに届けられるという流れは、とてもシンプルに見えるかもしれない。
それでも実際には、その流れの中に無数の関係性が含まれている。
当たり前のことだけれど、資材があって、道具があって、場所や設備があって初めてモノを作ることができる。
必要としてくれる人がいて、届けることができて、そのモノが使われる環境があって、初めてモノが生かされる。
その一つひとつの要素に、そこから広がる繋がりがあり、うまくバランスを保てなくなると消えていってしまう。

山田さんのお話で印象的だったのは「意味があって生まれて、その地域に根付いて、長く続いてきた何かがなくなってしまうことは、単体でみると “ただそれだけのこと” なのかもしれない。でも本当にそれでいいんだろうか?」という言葉だった。
その想いが根底にあるからこそなのだろう。商品を手に取ってくれる人々の暮らしに目を向け、自社だけではなく地域全体を巻き込んだ、共存、共栄を目指す玉川堂。
その大きな動きを生み出している中枢人物とも言える玉川堂番頭、山田立さん。
彼の目には、どんな世界が見えているんだろう。広く、多くを巻き込んで、ダイナミックに動き続ける原動力はどこからくるんだろう。それを知りたい、と思った。
届けるのは「モノ」だけではない
━━先日銀座の店舗でビールカップを購入させていただいたのですが、スタッフの方々の自社製品への愛情や誇りが伝わってきました。銅器の美しさだけでなく、その姿勢も素晴らしいと感じました。
ありがとうございます。それは嬉しいですね。
我々は、店舗スタッフ一人ひとりにモノづくりの現場を体感してもらう機会を作っています。一泊二日で新潟の本店/工場に来てもらい、職人の作っている姿を間近で見てもらうんです。実際に資材に触れ、下仕事を手伝うことも体験します。
そこで何か、感じることがあるのかもしれませんね。
逆に職人たちが店頭に立ち、実演や接客をすることもあります。お客さまに商品が渡っていく瞬間を経験してもらうわけです。
職人たちはこの仕事を一生の仕事にすると決めた、ストイックなモノづくり集団です。その一方で、お客さまと接する体験もまた大切だと考えています。
というのも、玉川堂は「銅器」を売っているわけではないからです。

━━銅器ではないとしたら、何を?
銅器を介して、我々はお客さまと「時間を共有している」と考えています。
いまの世の中、急須でゆっくりお茶をいれて愉しむ時間って、なかなか持てないじゃないですか。そういう昔ながらの生活リズムやスタイルを、うちの道具を使うことで思い出してもらうような、そんなゆとりや潤いのある時間を提供し、共有している。

そういった短い時間軸の共有と、もう一つは、長い時間軸の共有ですね。
我々は商品がお客様の手元に届いたときが、関係性の始まりだと考えています。
モノを育て、変化を慈しみ、修理をしながら使い続けていく長い時間を、銅器という道具を介して共有していく。
うちのお客さまの中には、修理をしながら一つの湯沸を三代に渡って使ってくださっている方もいます。ベテランの職人なんかは修理依頼の品をみて「自分が作ったモノだ」とわかるんですよね。
そういう長い目で見た時間軸の共有を実感できるのは、この仕事をするうえでの喜びでもありますし、玉川堂の商品の大きな特徴でもあると思っています。

━━200年続いてきた玉川堂さんだからこその、時間軸ですね。
そうですね。でも我々が関わることができるのは、その長い時間軸のほんの一部なんですよ。長く続くリレーの一走者でしかない、というか。
だからこそ、いま自分たちができることを全力でやり切って、次につなげていきたいと思っています。
長い歴史を振り返っても、玉川堂は色々な局面で変化し、進化し続けているんです。その場その場で踏ん張って、どうにかつないできた道を振り返ったときに、結果としてできていた道筋を伝統というのかもしれない。
そう考えると、いままでもこれからも、我々が貫くところは「銅を打つ」という部分なんでしょうね。それさえブレなければ、この先も玉川堂としてやることに制限はないと思っています。

暮らしの一部であるために
━━そんな玉川堂さんの銅器が、人々の暮らしのなかで、どのような存在であることが理想的だとお考えですか?
主役ではないけれど、暮らしの一部として身近に存在するモノ……といったところでしょうか。
やはり道具ですから、使ってもらってなんぼです。使うことが一番のお手入れにもなりますしね。伝統工芸といっても、現代のテーブルの上で使われないと意味がないと思っています。
━━大切にしているのは、あくまでも「道具としての価値」で選ばれるという部分ですね。
職人の手技ならではの価値はもちろんありますが、それを含めて無駄を削ぎ落とした「道具としての機能美」を大事にしています。
使っていただくための道具なので、時代の流れ、使い手であるお客さまの暮らしの変化にも敏感に対応していかなければならない。
例えば銀座の店舗なんかは、コロナ禍に突入する前までは売上の半分が海外のお客様に支えられていたんですね。
それは玉川堂は、湯沸や急須といった茶器を中心に作っているからです。お茶の種類は違っても「お茶を飲む文化」は世界中に根付いている。日本の伝統工芸という理由だけではなく、文化が根付いた暮らしのなかで使われる商品を打ち出しているからこそ、道具としての価値を持ち続けているんです。
日本国内に向けても現代の暮らしに合わせてコーヒーポットを作り始めたりと、変化に対応していく姿勢はいつも持ち続けています。

━━変わるものと、変わらないもの。という言葉が浮かびました。
そうですね。我々の商品は丁寧に使えば間違いなく人間より長生きするモノです。変化に対応しながらも、商品が手元に届いてから長くお付き合いのできる関係性を築いていくことを大切にしています。
一つのモノに愛着を持ち、必要に応じて修理しながら使い続ける日本の素晴らしい文化を残したい。モノを育て、慈しむことの喜びと豊かさを伝え、共有することが玉川堂としてできることだと思っています。
価値を伝える取り組み
━━工場を一般公開されていますが、それも時間を共有するという概念の一部ですか?
玉川堂が工場見学を始めたのは、実はもう数十年前のことなんです。その頃から希望する方には、工場を自由に見ていただいていました。
モノが作られる現場を見て、空気感を体感していただくことで、より商品の価値が伝わると考えています。
その体験が、価格に対する納得感につながります。すでにうちの商品をお使いになっているお客さまでしたら、使い方や、使うときの気持ちの変化につながったりするものなんです。
だから、現場に来て、体感していただきたい。
築100年を超える母屋の風情や、職人たちの銅を打つ音が鳴り響く工場の雰囲気を、肌で感じ取ってもらいたい。
それが、この技術を次世代に残していくための、一番の方法だと思っています。

━━次世代へ残していくために。
そう、この地域に200年根付いてきた想いや技術を次につないでいきたいんです。
そのために何ができるか、という視点で考えてみると、やるべきことはたくさんある。
例えばうちのお客さま方が「最近こういうものが愛おしく感じるのよね」と話してくださることがあります。私はそのきっかけが、いったいどこにあったのだろうと考えるんです。
きっかけは人それぞれで、絞り込めるものではないのかもしれない。ただ少なくとも、主体的にきっかけ作りをやっていく必要があると、数年前から考えるようになりました。
燕三条という地域は古くから「金属加工の町」として知られています。金属だけでなく様々なモノづくりの、素晴らしい技術が根付いている。本当に魅力的な地域なんです。
でも、地域の子どもたちや若い世代の人々にその価値が伝わっているかというと、あまりそういう実感がわかないんですよね。
だから私たちは、子どもたちが自分たちの育った地域の魅力や素晴らしさを知るきっかけを作っていきたいと思っています。
でもそれは「将来ここに残ってほしい」という押しつけがましいものではありません。伝統をつなぐことに直接かかわらなくてもいい。生まれ育った地域に自信と誇りを持って、世界で戦える人材になってくれたら十分。
それが結果的に、地域の発展、伝統工芸が次世代に残っていくきっかけになっていくんじゃないかと思っています。
つながり、広げ、残していく
━━だからこそ、積極的に地域を巻き込んで活動していらっしゃるんですね。
玉川堂が単独でできることはそう多くはないと思っています。うちだけでたくさんの人を呼ぶというのはどう考えても難しいですよね。
玉川堂がずっと続けていた工場見学が、地域を巻き込んだ「燕三条 工場の祭典」という大きな流れに育っていったのも大変ありがたい大きな変化でした。


燕三条という地域全体が活性化することで、自社も潤う。地域を見て回って、楽しんでもらうことが目的としてあって、そのなかで選択肢の一つとして玉川堂を選んでいただけたらいいと思っています。
ここはモノづくりの工場が多い地域です。飲食や観光などの別業種ともつながって、地域の魅力を多くの方に知ってもらえれば、我々自身のことだけでなく、広い範囲で次世代へのつながりに貢献できると考えています。
別の地域との連携も視野に入れ、つながりを広げていくことが、伝統を残していくためには必要なんです。
━━繋がって、広がって、残していく。
そういうことです。
いろんな意味でつながっているんですよ。
ここ数年間の玉川堂は、ありがたいことに1〜2名の採用枠に40〜50名の応募があるほどです。現在は職人の平均年齢も30代半ばと若く、後継者という部分ではしばらく心配はありません。
ただ、道具を作る職人さんはどんどん廃業し、副資材がなくなる事態も起きつつあります。
例えばうちで作っている湯沸の取手に使っている葛(かずら)をとる人は、もういなくなってきています。もしかすると、もうすぐ手に入らなくなるかもしれない。

それはもう仕方ない、と言ってしまえばそれまでなのかもしれませんが、「いま何か自分たちにもできることがあるんじゃないか」と、そんなふうにも思うんです。
今できることを、愚直に続ける
━━次世代につないでいきたい。山田さんのその強い想いはどこからきているんですか?
どうでしょうね。自分でもよくわかりません。
ただ、意味があって生まれて、その地域に根付いて、長く続いてきた何かがなくなってしまうということは、単体でみると “ただそれだけのこと” なのかもしれない。でも本当にそれでいいんだろうか? と思うんです。
ずっと続いてきた長い流れの中で、自分たちが関わることができるのはほんの一部でしかない。それを自分たちの代で、なくしてしまっていいものなのか、と。
それはノスタルジーだけではないし、つながなくてはならないという義務感でもない。
いま動くことで起こる変化が単純に楽しいんです。
伝統産業という分野では、多くの現場で職人さんの高齢化や、次の担い手不足が深刻な問題になっています。そういった別の産地との共同の取り組みや、地域同士の観光面でのつながりも視野に入れ、想いや技術を残していきたいですね。
そのためには、いまできることを愚直にやっていくしかない。
自分たちの手の届く範囲のことは自分たちでよりよくして、次に残す。
それを受け取った次の世代の人が、その時代でやるべきことを考え、取り組んでいけばいいと思っています。