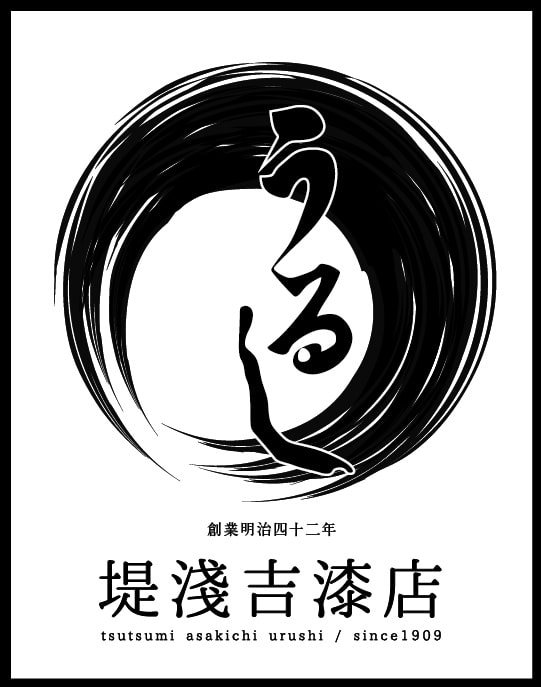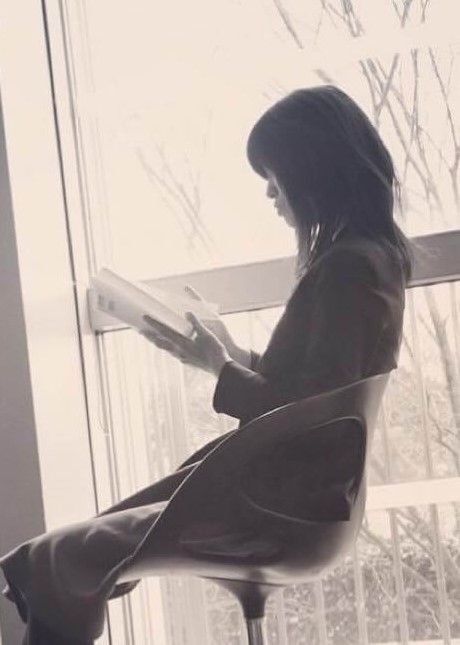Photo:Ryan Jones(SHIN&CO.)
Text by 江指美穂
波が覆いかぶさってくる。
息ができない。
サーフィン初心者の私は大きな波を越えられず、なかなか沖に出れなかった。
みかねた友人が「ボードを持って先に行くから泳いで沖まで来て」と、すいっとボードを持って沖まで出ていってしまう。
当時住んでいたベネズエラの首都カラカス。
車で30〜40分ほどで着く海に、私は毎週末通っていた。
検問を抜けるとパッと海が広がり、坂の下にキラキラ光って美しい。
2017年、政情不安が続くベネズエラ。
大変な生活のなかでも、市民はみんな海での時間を楽しんでいた。
友人は「今月はまだ海に行ってないから行かないと!」と言い、近所の人は「週末は海には行った?」と聞いてきた。
「もちろん海は好きだし、行きたい! でもみんな海どころじゃない生活なはずなのに」と私は思った。それほど彼らにとって海は、憩い、安心、希望、つながり、そして人生の一部なのだ。
……だから、軍が撃った弾に当たったとか、デモに巻き込まれたとかならまだしも、溺れて死んだなんて洒落にならない。
必死にもがいていたら、近くにいた人が助けてくれた。
しばらく呆然とする。
怖い。
でもこのまま入らないとどんどん入れなくなる。
気持ちを切り替えてもう一度波に向かった。
自然は怖く、そして美しい。
どれだけ生活が苦しかろうが、触れたくなる。
いつも美しくそこにあって、でもなめてかかるとちっぽけな私たちを大きなうねりで諫める。
いつから私たちは自然が自分の日常と関わりがなく、仕事の休暇を取るまで触れ合えない遠いものにしてしまったんだろう。
こんなに大きく、美しく、楽しいものなのに。
*
「サーフボード × 漆」
「伝統」で検索していたところ、こんな文字に出会った。そんなコラボレーションはありなのかと、ウェブサイトに見入る。
株式会社堤淺吉漆店の堤卓也さんのインタビュー記事だった。
堤淺吉漆店は明治42年(1909年)創業の漆の精製をする老舗だ。
四代目の堤さんは、専務取締役を務めながら、漆工芸と自然を身近に感じてもらうための活動を幅広く展開している。
自身が好きな自転車、スケボー、一枚木のサーフボード・アライアなどに漆を塗り、伝統とスポーツを掛け合わせ、自然を考慮する取り組みだ。

また、一般社団法人パースペクティブ共同代表を務め、漆の木の植栽をされたり、漆の持つ可能性や魅力を冊子や映像を通して伝える「うるしのいっぽ」の活動をされている。
これだけを見ると「今っぽい活動をされている人」という印象を受けるかもしれない。
しかし、日光東照宮や姫路城などの重要文化財や国宝の修復にも用いられている漆「光琳」の開発に携わるなど、堤淺吉漆店の2020年三井ゴールデン匠賞の受賞に貢献されている。
(三井ゴールデン匠賞:日本の伝統を継承しながら未来につながるものづくりに真摯に取り組み、さらに発展させている伝統工芸の担い手の活動に授与される賞)
日本の工芸、漆産業において重要な活動をされ、評価されている方だ。
お話した堤さんはとても自然体。言葉の端々から漆への愛情があふれ、漆がある森を大切につないでいきたいという信念がある。
「自然は美しい、そして怖い。人間は大きな波がきたら抗えないし、雪崩が起きたらどうしようもできない。与えたり奪ったりする。でも生きるってそういうこと」
そう語る堤さんの構想は壮大だ。
伝統を超えた想いをもっと知りたいと思った。
「漆はかっこいい。」堤さんがみる漆の魅力
──伝統の漆とサーフボードなどの組み合わせに驚きました。これまでなかったその発想はどこからきたのでしょうか?
ただ好きなものに漆を塗りたいと、シンプルに思ったんです。最初からメッセージ性があったわけではありませんでした。
友人たちもほとんど漆のことは知らない。そこで2006年頃から続く「自転車ブーム」に乗るかたちで自転車に漆を塗り、注目を集めたいなと思ったんです。売り物としてではなく、ただ知ってもらいたい気持ちが大きかったです。
これまでもスケートボードなどに漆を塗ったものはあったのですが、あくまでも鑑賞用のもの。そうではなく「塗って使える」のがかっこいいと思っていました。

──漆が “かっこいい” というのは新しい感覚です。
子どものころ、漆の仕事をしていたおじいちゃんの影響が大きいと思います。
おじいちゃんは図工の時間に作った飛行機の羽が折れたら、漆でくっつけてくれました。いまでいう金継ぎみたいなものです。自分のものは自分で作って、あるもので直す姿がかっこよかったんです。
もう一人大きな影響を受けたのは、世界的ウッドサーフボード・シェイパーのTom Wegener(トム・ウェグナー)さんです。
トムさんは、古代ハワイアンが乗っていた木製のサーフボード「アライア」を現代に甦らせた方。通常使われているボードは石油由来であるため、環境に負荷を与えてしまい、ゆくゆくはゴミになってしまう。でもトムさんは、庭で木を育てて、アライアを削って出た木くずも森に戻してボードを作っているんです。
映画『スプラウト』で語られているトムさんのライフスタイルと、僕のなかの漆のイメージがリンクして、アライアに塗れば意味があると感じました。
──漆のどんなところに引き込まれたのでしょうか?
漆の樹液って生き物みたいなんです。精製するうちにちょっとずつ水分は取れて質量は減っていくのに、ふくらんでいく。色も最初はカフェオレみたいな色から段々となまめかしい、艶っぽい色に変化していきます。これは塗膜(塗られた塗料が固まってできた膜)になるともう出せない色です。

あと、漆に触れるとしっとりさらさらしていて、赤ちゃんの肌のようで気持ちがいい。
実際は車の塗料のウレタンよりも硬いのですが、漆は水分を含んで固まるので、脳が錯覚して柔らかいと感じるそうです。
人間も水分でできているから、自分と近いものに触れると気持ちいいのでしょう。その触り心地から、昔から日本人はお椀に口をつけて飲んできたのではないかと個人的に思っています。

そんな漆の状態を観察し、見極め、お客さんの要望にあった漆を精製していく。生き物だから翻弄されることもありますが、そこがまた面白くて、美しい。
漆を残していきたいと思うようになりました。
漆業界の課題と漆が果たすべき役割
──魅力にあふれた漆ですが、他の伝統産業と同様に衰退傾向にあるものだと思います。大変な家業を継いでしまったと感じたことはありませんでしたか?
思わなかったですね。これまで漆のことを知らないできたので、必死で漆の精製技術をあげて向き合っていく日々でした。ただ漆業界の現状を知れば知るほど、危機感を抱くようになりました。
40年ほど前は年間500トンだった生産量は、いまは30トンほどになっています。しかもそのほとんどが中国産で、国産漆はわずか1.8トン。数年前までは国産漆を取る漆掻き職人さんは70〜80歳の方がほとんどでした(現在は若い人も増えています)。
中国視察でも、同じように高齢化が進んでいる状況を目の当たりにしました。輸入量も減少しています。
でもどうやったら漆を増やせるのか。
僕は、かっこいいプロダクトを作って売る能力もないし、生産するお金もありません。木を増やすことも大変だし、儲からないとわかっている漆業で家族を養えるようなアイデアもない。
漆屋にできることは何もないと思えて、絶望感でいっぱいでした。
なんとか自分の世代まで持てばいいかなと甘い考えでいた頃もあったのですが、子どもができて真面目に向き合うようになりました。
子どもたちの時代では、海が汚れて入れなくなったり、僕たちが楽しんだパウダースノーを温暖化で知ることができなくなってしまったら……。
そんな状況は許せないなと思いました。
漆が生息できる自然を、子どもたちに残していくために始めたのが「うるしのいっぽ」の活動です。まずは漆について知ってもらいたいとあがいた一歩でした。
漆掻き職人さんなど、これまで知られてこなかった漆の生産現場について伝える冊子や映像を通して、漆の魅力について発信しています。
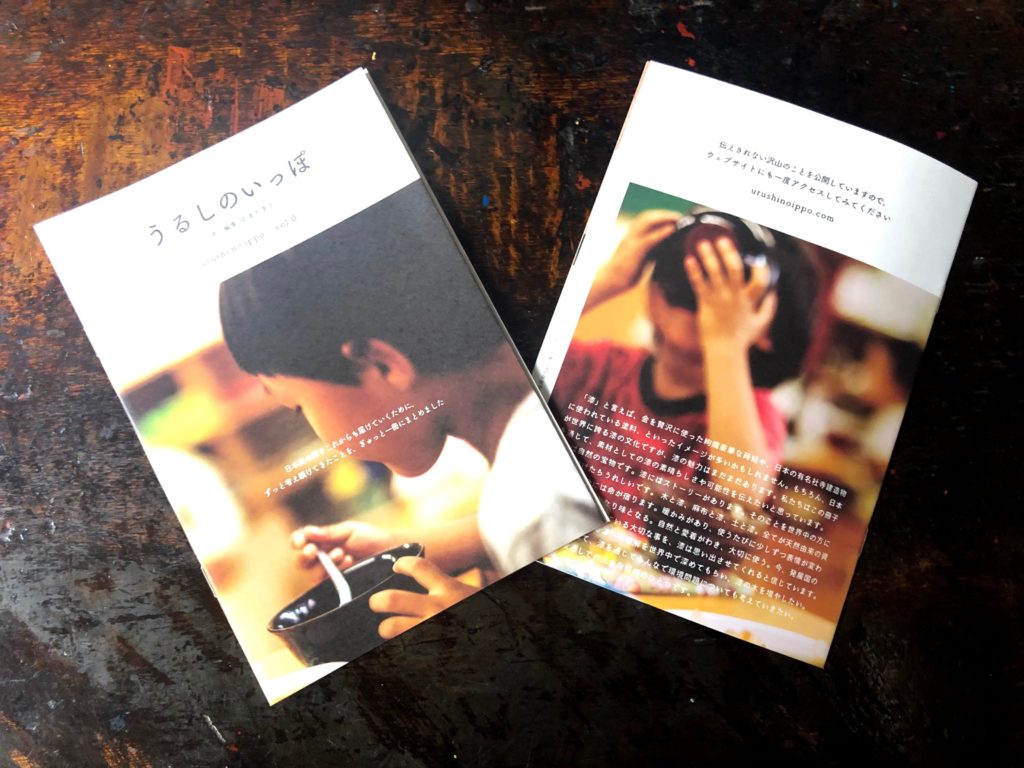
──漆の魅力の伝え方が漆製品を売るのではなく、情報や経験を通して感じてもらう点を大切にされていることが印象的です。
僕にはおじいちゃんからつながってきた漆の伝統、そして「漆はかっこいい」という感覚がある。それを伝え、残していくためには漆を使って、漆に対して共感してもらうことが必要だと考えています。
そこで、天然一枚板から削り出したアライアを漆塗りで仕上げ、その制作から波に乗るまでの過程を映画『BEYOND TRADITION』に収録しました。そうした映像を観てもらうことで、自分たちにとって身近でいいものだと知ってもらいたいんです。

知ってもらう機会が増えれば、漆の価値を違うかたちで創造してくれる人が現れる。そうすると、いままでは伝わらなかった人たちのところに届く可能性が出てきます。
漆は「つながるためのツール」なんです。
だから漆を売るのではなく一緒に使いたい。それができたらまずは十分だと考えています。
──つながるツールとして、サーフボード以外に進められている異分野とのコラボはありますか?
いま京都の塗師、木地師さんたちと進めているのは、アサギ椀プロジェクトです。浅葱(あさぎ)椀は、「江戸時代の京都で日常的な食器として愛用されていたお椀」と文献に残っていたものです。京都の地元のひのきを使い、なつめを引く技術を用いて、京都の漆器づくりを行っています。

もう一つは、漆と木で作ったストロー「/suw」です。切った木の根元はチップになるだけだったので、せっかくならその木を利用したいと思い、吉田木工の吉田さんと始めました。
これまでも木のストローはあったのですが、耐久性や衛生面が十分ではなく、1回の使用だけで使い捨てにされてしまうことがありました。この「/suw」は木に和紙と漆をほどこすことで何度でも使ってもらえるストローです。

だけど、漆をプラスチックの代わりにしようと考えてはいません。安易にものを作りたくないんです。そうなれば大量生産・大量消費になり、ゴミになってしまいます。環境にいいからといっても、使う人間が変わらないとなんにもならないですよね。
モノを作るってすごいことです。
モノにあふれるいま、モノを作ることはすごく責任を伴います。どういうものを作ることがよりよい次の世界につながるかを考えなければ、意味がない。
だからこそ、みんなでモノづくりをする時に工芸が役に立つ。意味があるんです。
世界、そして次世代に広がる輪っか
──「モノづくりに役立つ工芸」についてもう少し詳しく教えていただけますか?
漆などの工芸は、自然素材を使った人の手によるモノづくりです。機械のように複雑ではなく、もっと身近で自分で体験ができます。体験するとモノづくりに敬意が払えるし、モノに愛着が生まれます。
モノに愛着を持てると、使い捨てようとは思わない。どうすれば長く使い続けることができるのかとデザインへの意識も変わってくるはずなんです。
そうすれば自然への負荷が減るモノづくりができるようになると思っています。
──工芸を通して人と自然との距離が近くなって循環が生まれるんですね。
はい。かつては森や自然が近いから当たり前だった感覚です。森では鳥が鳴いていて、歌が生まれ、芸術が生まれ、そこから文化がすべて生まれてきました。
いまは昔の人たちが一生懸命いろんな技術を革新させて、便利になった。でも結果として自然も壊してしまい、地球は大変なことになっている。そう気づいたのならその技術を正しい方向に使って、直せばいいんです。
べつに江戸時代に戻りたいとかそういうことではないんです。僕もガソリンを使って車を走らせ、サーフィンに行きます。人が生きているだけで壊している側面もあります。
だから、自然素材を使ったモノづくりといまの技術の両方を使って、どうやったらみんなの幸せになるのかと楽しく考えていけたらいい。漆や工芸はいまの自分たちの暮らしや環境について考え直すきっかけになると思っています。

──ここまでのお話を伺い、サーフィンを起点にさまざまなプロジェクトが大きく動き出した印象を受けました。
海外の展示会などでも漆塗りのアライアのサーフボードを見て説明を聞いてくれて、みんな「Amazing!」「Fantastic!」って言ってくれるんです。
サーフボード自体もすごくいいと言ってくれるのですが、一番称賛してくれるのは漆を縄文時代から人がつないできたということ。それは日本人がもっと誇りにすべきことです。そこももっと伝えていきたいなと思っています。
次の世代を思っていま植える、昔植えてもらった成木の樹液を採取する、その漆を使ってモノを作って、使って、修理してまた使ってもらって……そんな時間軸がずっとつながってきているのはすごいことです。
僕はサーフィンがきっかけになったけれど、どんな入り方でもいいと思っています。

ー今後どんな風に活動を広げていかれるのでしょうか?
2つ取り組んでいることがあります。1つは、京都の京北でサーフボードを作る工房を自分たちで作っていることです。
いろんな方々の協力を得て、工房ができてきています。京北の木を使って小屋の床に漆を塗って作っているのですが、この小屋がとてもかっこいいので早くお披露目したいです。
これまでもいろんな取り組みを一緒にしてきた、木工サーフボード職人ロドリゴ・マツダが京北の木を削って作ったサーフボードを販売する試みも予定しています。
サーフボードを買ってもらえなくても試乗会に参加してもらって、自分たちの精神、波を分け合ってもらう。そしてリペアワークショップを通して自分で漆を使って触れてもらう。この工房を通じて漆や工芸を見てもらえるし、使ってもらえます。
山で作ったものを使って海で遊んで、山と海がつながっていることを感じる。そして、地元の木を使って作り、モノを大切にする気持ちを持つ。
そんなことができる場所です。

もう1つは、映画『OCEANTREE〜The Journey Of Essence~Episode. 2 in Kyoto』がまもなく上映されることです。
映画のきっかけは、去年の秋、プロサーファーの石川拳大、藍染プロダクトデザイナーの永原レキ、木工サーフボード職人ロドリゴと工芸とサーフィンをつなぐ旅をしたことです。
徳島からスタートして四国を波乗りしながら、組子や和紙の職人さんたちを訪ねました。その道中で、伝統工芸、地産地消によって大量生産を考え直すことを伝える映像ができたらいいなと話をしていたことをかたちにしました。

こうした映画を通して関心を持ってくれる人の輪が広がっています。
あと、取り組みではないのですが、ハンドプレーンという手にはめる小さいサーフボードを子どもたちと作ったりしています。山で一緒にまだ乾いていない状態の柔らかい木を楔とハンマーで割って乾かして、焼きペンで絵を書いて漆を塗ります。
自分たちが遊ぶものは自分たちで作る、地元の木は地元で使うことがかっこいい。その文化を子どもたちにとっての当たり前にしたいと思っています。
大人たちが本気で遊んでいるところを子どもたちに見せて、「こんなの面白いな」「こんな選択肢もいいな」と思ってもらいたい。
それができたら、もっと輪っかが広がると思います。

いまいろんなことがつながってきているから、自分のなかでは気持ちよく活動できています。
おじいちゃんから自分につながっている。それを漆を通して伝え、つなげていける。それがうれしい。
ちょっと動いた先に共感してくれる人がいることを実感しています。その人たちと世界を変えることができたら。そう思っています。