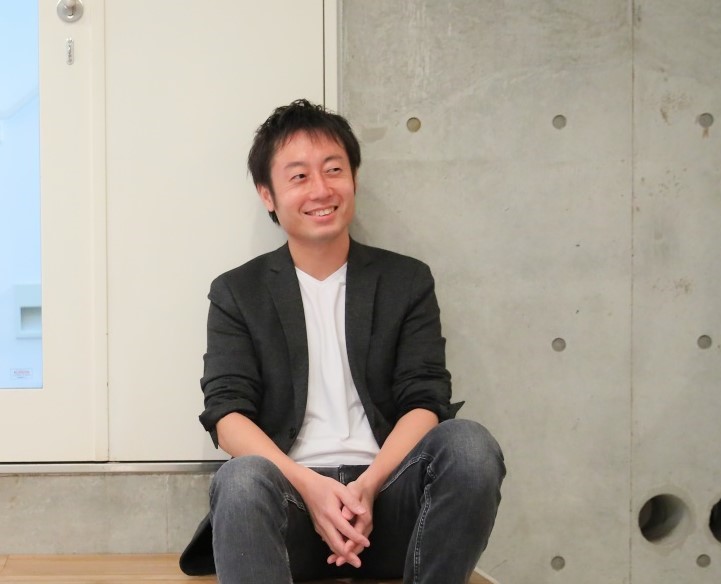写真提供:合同会社シーラカンス食堂
Text by ながいしほこ
ボロボロの黄色いアメ車に乗って、海辺のジュエリースタジオに向かう。
ボスが好きな音楽を大音量で聞きながら、毎日作って笑って、また作る。
カリフォルニアの小さな町でジュエリーアーティストのアシスタントとして働いていた頃、私にとってモノづくりは、純粋な楽しみであり、喜びだった。
作ることが楽しくて、作っていられたらそれだけで満足だった。
日本に戻ってから、たまたま近所にあった彫金工房を尋ねた。
そこで出会ったのが、いわゆる日本の伝統的な彫金職人だった。うまく言えないけれど「モノづくりの深みに触れた」ような気がした。
それ以来私は、その彫金工房に通い詰めることになる。
知れば知るほど、職人の世界に惹かれていった。
日本独自の卓越した技法や技術だけではなく「積み重ねていくもの」の重み。歴史を重ねてきたものだけが纏うことができる、文化という価値。
ゴツゴツした職人の手が、指が、静かに張り詰めた背中が好きだった。
丁寧に手入れされ、使い込まれた道具たちは美しかった。
職人が語る昔話は興味深く、仕事への誇りと愛情に溢れていた。
あの工房で過ごした時間は、私に大切なことを教えてくれた。
目の前のものを大切に扱うこと。
完成までの道筋を思い描くこと。
ひとつひとつの工程に手を抜かず、順を追って丁寧に仕上げること。
自分の内面が、現象として外の世界に現れてくること。
積み重ねてきたものへの敬意と、積み重ねていくことの大切さ。
今の私は、職人の世界とは少し離れたところで生きている。
それでもあの世界に触れたことで、感覚的に染み込んでいった多くの事柄は、私にとってかけがえのない財産だ。
私たちはもっと、知るべきなのだと思う。
自分の暮らしがどんな物事で成り立っているのかを。何がどこからやってきて、そこにどんなストーリーがあるのかを。
*
合同会社シーラカンス食堂の存在を知ったとき「救世主だ!」と感じた。
伝統産業を取り巻く問題の多くは、幾重にも固く絡まった毛糸玉みたいに、どこからほどいていったら一本の糸に戻るのか検討もつかないほど複雑だ。
モノづくりの技術を磨くこと、その文化を受け継ぐことに人生を捧げてきた職人さんたちには、少しずつ絡まっていく糸をその都度ほどいている余裕などない。
気がついたらその絡まりはどんどん固く大きくなっていて、どうしようもないところまできてしまっていたというケースが多い。
労働条件が過酷、モノが売れない、後継者がいない。
受け継がれてきた伝統が、この技術が、自分の代で途絶えてしまうのはやるせないが、明るい未来が見えないならば、それも仕方がないのかもしれない。
そんな葛藤を抱えている職人さんたちが、きっと全国に大勢いるのだと思う。
一つひとつの問題をバラバラに解決するのではなく、全体的な流れを把握して、根本的解決に導いてくれる存在が、彼らには必要なのだ。
しかもそれは、職人の世界に対する心からの敬意とモノづくりへの愛情を持ち合わせている「誰か」でなければならない。彼らの受け継いできた伝統と文化を守るためには。
デザインスタジオ、シーラカンス食堂の事業は多岐に渡る。
時代にそったデザインを武器に、海外に販路をひろげ、時に古いしきたりを大胆に改革してでも後継者育成に取り組んできた彼らの軌跡は「カタチを変えてでもつないでいく」という決意の現れだ。



「お仕事の様子を見せていただけませんか?」というお願いを快諾してくださった小林さん。
後継者育成事業のために仲間と手作りで作り上げた工場を案内しながら、工具や作品について語ってくれた小林さんは、とても楽しそうだった。
モノづくりへの深い愛情と、受け継がれていくものへの敬意を感じた。
問題解決のためのデザイン
━━後継者を育成するために、これだけの工場を手作りされるなんて熱意がなければできませんよね。シーラカンス食堂さんの活動内容をはじめて知ったときにはその幅広さに驚きましたが、このバイタリティで事業をひろげていかれたんだろうと納得しました。
デザインスタジオ、ということですが、小林さんは「デザイン」をどのように定義されているんですか?
ぼくにとって、デザインは問題解決のツールです。
「なんとかしたい」問題がある。特に伝統産業に関するそういった問題を、得意なデザインというツールで解決していこう、というのがぼくたちの仕事です。
最終ゴールが問題解決なので、プロダクトやグラフィックの「デザイン」という、一般的に連想されるような事柄だけにはおさまりません。
ぼくがデザインという言葉を使うとき、それはなんていうか、もっと包括的な意味合いだったりします。

──積極的に伝統産業の問題に取り組んでいることに、何か理由はありますか?
実家が表具屋で、小さい頃からモノづくりが身近な存在だったことが大きいですね。そういう環境で育ったぼく自身、モノづくりが好きな子どもでした。
祖父母の時代、表具屋は繁盛していました。祖父母は早々に引退して、両親が仕事を引き継いだわけですが、いつからか父親が暇そうにしているのを見かけることが多くなりました。
父親から「世の中の住宅が、ハウスメーカーが作るものに変わってきている。職人が必要なくなってきている」という話を聞いたりして、子どもながらに理不尽な気持ちになったのを覚えています。
「いったい、何が原因なんだろう?」
原因を逆算して構造的に考えることが好きだったぼくは「表具屋とは、表装文化とは何か?」といった部分にまで問いを深めるようになりました。
──そのように考え出したのは、いつ頃からですか?
中学生くらいでしたね。
でも当時、自分の進路については深く考えず、地元の進学校に入学しました。
幸運だったのは、高校で出会った美術の先生の影響で「デザイン」というジャンルに出会ったことです。
そのとき、喜多俊之さんというデザイナーを知って衝撃を受けました。
彼は紙すき和紙をイタリアの有名家具ブランドの照明器具に取り入れて、それが世界的に売れていたんです。
あぁ、ぼくがやりたいのはこういうことだ。衰退していく日本の伝統産業が、現代の暮らしの中で価値あるものとして受け入れられるようなカタチを作りたいんだと。
自分の方向性がそこで固まりました。高校1年生のときでした。
──最初にデザインというものに出会ったときから、もうそれは問題解決のツールだったということですね。伝統産業が抱える問題は様々だとは思いますが、根本的原因として思い当たることはありますか?
自分の中で大枠の答えは出ていて。
合理化・平均化による文化の衰退が、そのまま伝統産業の衰退につながっているとぼくは考えています。
たとえば表具でいうと、襖や障子は海外のドアとはあきらかに目的が違う。
湿気が多いなど、日本の風土にあった特質はもちろんありますが、それだけではありません。屏風や掛け軸なども含めた表具は「場を作る」ためのものでもあるんです。
昔はケの日ハレの日、家族が集まるという習慣がありました。
「張り替えができる」という性質をもつ襖や障子は、安価で綺麗にできて、場を整えることができる。掛け軸はその場に応じて掛け替えることで、場を演出する。
表装文化はそういった生活のなかで受け継がれてきたもので、その文化の元で表具は愛され、必要とされてきました。
それが現代では、結婚式もお葬式も、お金を払って専用の場所で行うのが一般的になった。そのほうが合理的だからです。
そうなると、表具が必要とされる場は少なくなっていく。
色々なケースがあるけれど、伝統産業が抱える問題の根本は「文化の衰退」によるものが大きい。そこを「なんとかしたい」と思っています。
日本には独特の「積み重ねていく」文化がある。この想いは、海外に目を向ける機会が多くなればなるほど強くなっています。
この文化こそが日本人のアイデンティティであり、世界で活躍できる強みだと感じるからです。
一方で、日本文化の衰退がものすごい勢いで進んでいるという強い危機感も持っています。
今、イノベーションが必要な理由

──日本文化が衰退している。それはご実家の表具屋さんや、シーラカンス食堂の事業を通して伝統産業に深く関わってきた小林さんが肌で感じていることですか?
そうですね。
ヨーロッパ諸国からすると、日本は羨ましい成長の仕方をしているのだと思います。
先進国でありながら、昔ながらの伝統産業を多く残しているような。
意外かもしれませんが、ヨーロッパの国々は伝統産業を無くしてしまっている状況です。残っているのは、国が守っているものばかり。人々の暮らしとはかけ離れた場所でしか残っていないんです。
だからこそ、日本のモノづくりに敬意と憧れを抱いている。
でも実際は、もうギリギリなんですよ。
いま手を打たなければつないでいけない。そういうところに来てしまっているんです。
世界には「積み上げてきたもの」と「突然やってくるもの」という2種類があります。
「突然やってくるもの」は短い期間に完成されて、すぐに消えていくような何か。
「積み上げてきたもの」は、当然ですが長い年月をかけて積み上げてきたからこそ価値を持つものです。
積み上げていくにはものすごく時間がかかるのに、消えてしまうのは一瞬。ぼくはこういう仕事をしているのもあって、一瞬にして消え去っていくものをたくさん見てきました。後継者問題がまさにそうです。当然次につなぐ人がいなければ消えてしまう。
だからこそいま、カタチを変えてでも、なんとかしなければいけない。
その使命感から始めたのが「販路開拓」と「後継者育成」です。
──なぜその2つの手段が大切だとお考えになったのでしょうか?
根本的な問題解決には、必要不可欠だと判断したからですね。
どれだけよいものを作っても、売れないと続けられない。売れたとしても、そもそも作れる人がいなければ続かないじゃないですか。
ぼくたちのクライアントさんが抱えている問題は複雑です。多くの場合、クライアントさん自身も何から解決すべきなのかよくわかっていません。
たとえば播州刃物のケースでも、最初の依頼は「新しいハサミのデザインを考えてほしい」という内容でした。
しかし、お話を伺ってみると単価や流通面、後継者問題など多くの問題が複雑に絡み合っていることが見えてきたわけです。
それらの問題点の一部分を改善しようとしても、単純な問題ではないので根本的な問題解決には至りません。
ぼくたちは、それぞれのケースによって問題の根っこを探っていくところからスタートして、根本的解決を目指します。
当然ですが扱うモノや産業によって、問題点も解決策もまったく違ってきます。
正解があるわけではないし、やってみなければわからない部分も多い。ぼくたちも手探りで進んできて、いまに至ったという感じですね。
現在は日本をベースに、ヨーロッパはオランダとドイツ、オセアニアはメルボルン、北米はロサンゼルスとニューヨークから海外へ販路を広げていて、後継者育成事業にも力を注いでいます。
暮らしに根付いてこその伝統産業
──販路を海外に広げたのは、何か狙いがあったからですか?
狙いというよりは、必然的にそうなったというほうが正しいかもしれません。
最初のきっかけは学生のときに出展したミラノサローネです。(イタリア、ミラノで毎年開催されている世界最大規模の家具見本市)
日本でも展示会出展の経験はありましたが、ミラノの展示会で得た反応はまったく違うものだったんです。ヨーロッパの展示会で出会う人々は、個人個人がモノの良し悪しを自分の軸で測っているという印象を受けました。
一方、日本の展示会で出会うバイヤーさんには、決定権がないことが多いんです。決めるのは上の人で、情報収集をしにきているだけというか。
個人の感覚、好き嫌いといった感情は必要とされないので、展示会で話をしても目の前の人の気持ちがわからない。
ぼくはこういうところでも、流通の合理化・均一化という日本の問題が浮き彫りになっていると感じています。大手が商店街などに代わり、地方の小規模事業者が壊滅状態にあるわけです。
ヨーロッパでは、中小規模の企業や自営業の小さなお店が各地域で元気にやっていて、店主が自分のこだわりで展示会などで商品を買付するのが当たり前です。店主とコミュニケーションも取れるし、その場で実際に取引ができる。
展示会で反応の違いを体感して、海外の人の方がわかってくれるという肌感覚から、積極的に海外の展示会に参加するようになりました。
そこで得た人脈や経験を生かしていったという流れです。

──海外で実際に手応えを感じたからこそ、広げてこられたわけですね。
はい。
ただ、「日本のモノはいい」というある種の憧れのような部分で購入につながったとしても、それだけでは暮らしに根付いていかない。
伝統産業品は、暮らしのなかで使われてこそ受け継がれていくものなんです。
商品を売って終わりではなく、暮らしに根付くまでのプロセスを考え、そのために商品を開発する。
だからぼくたちは、海外の卸先などで刃物研ぎのレクチャーなども実施しています。
たとえばヨーロッパ諸国の方が、見た目のデザインと切れ味だけで日本の包丁を手に入れても、大理石のまな板の上で使ってしまってはすぐに刃こぼれを起こしてしまいます。
日本の包丁は柔らかいまな板の上で使い、定期的に研ぐことで切れ味をキープすることができる。日本の包丁は、研いで長く使えることが本質ですからそれを伝える。
そうやって使ってもらってこそ、本当に良いモノとして暮らしに根付いていくんです。
「根付かせる」という問題をデザインで解決するという視点から、砥石のコンプリートセットや『UKEMI』という名のまな板が生まれました。
──『UKEMI』は柔道の「受け身」から?
はい。柔道は世界的なスポーツで、「受け身」という言葉も意味合いと共に浸透しています。この名前にすることで、まな板の役割まで伝わると考えました。
商品が道具の作法を伝えるというか。コミュニケーションが取れるデザインを心掛けています。

時代に順応したモノづくりと文化の継承
──そうして暮らしに根付いていくモノづくりを未来へ残すためには、後継者育成事業は必然だったということですか?
伝統産業における後継者問題は深刻です。
地元の刃物産業に深く入り込んでみてわかったのは、職人さんたちの高齢化が進んでいるということです。彼らの多くは自分の技術を人に伝えたい気持ちはあっても、実際に後継者を受け入れることは難しいという現実があります。
非常に大きな課題にもかかわらず、ぼくたちもこれといった解決策を見出せないまま時間だけが過ぎていく時期がありました。
そんな折、全国で高く評価されている盆栽バサミを作っていた職人さんが、認知症の発症が原因で突然引退されるということが起こりました。
ぼくたちはアメリカにその職人さんのハサミを卸していて、現地でとても人気のある商品でした。
本当によいモノが突然途絶える。
長く続いてきたものが消え去るということをダイレクトに体験したとき、ぼくのなかでスイッチが入りました。
伝統産業の世界では「技術の継承のためには弟子を育てる」という形が絶対的で、それまではぼく自身も「弟子入りでなければ継承できない」と思い込んでいました。
ただ、もういよいよ後がないという状況に直面して、その思い込みを捨てたんです。
「弟子入りではなく、新しく工場を作り、そこを拠点に自主的に学べたらどうか。わからない部分は職人さんたちに教えてもらう。この方法なら、職人さんたちの負担も軽く、後継者の育成もできるのではないか」
これしかないと思い、祖父母の作った中庭を自分たちの手で均して、手作りで工場を作りました。
──伝統産業の世界では型破りな方法ですが、周りの反応はどうでしたか?
もちろん、そんなやり方で技術の継承ができるわけがないなど、否定的な意見も多かったのは事実です。
それでも実際に動き出してみたら、熱意が伝わったのか、協力してくれる人が周りに増えていきました。
いまでは職人さんたちも何かと気にかけてくださって、熱心に指導いただいています。

──工場は具体的にどのように運営されているのですか?
工場で実践しているのは、昔ながらの火造り鍛造(たんぞう)という技法です。
軟鉄の棒と鋼を鍛接して刃物を作っていくこの技法で刃物を作っている職人さんは、今ではもう数えるほどしか残っていません。
安さとスピード重視だった時代の金型を使って量産するという製法は、産業形態が大きくなければ成り立たない。
今後、刃物産業を継承していくには基本の「火造り鍛造」に戻るしかないんです。もっと言うと、様々な鍛治仕事ができる「自由鍛造」を目指したい。
そうは言っても、一人前になるまでに10年はかかると言われている職人の世界です。それまで利益が出ない状況では、技術を継承する前にぼくたちが倒産してしまう。
継承のためには利益を出して、工場を続けていかなければならない。
その問題を解決するために、『富士山ナイフ』のデザインと製造販売を始めました。
『富士山ナイフ』は金型を使った半量産品ですが、工場で『富士山ナイフ』を作ることにはメリットがあります。
一つは利益を出せる。ぼくたちは販路を持っているので。
もう一つは、ナイフを作ることで刃物の仕上げ工程を学ぶことができるという点です。仕上げ工程は火造り鍛造での刃物づくりにも必要な技術なので、無駄にはなりません。
あくまでも後継者育成を目的としているので、月の半分以下の時間で『富士山ナイフ』を作る、残りの半分以上の時間は火造り鍛造の鍛錬に当てる、というルールで運営しています。
──とても丁寧に考えられていますね。ただ、職人の世界は合理性とはまた違った価値観で成り立っている部分も多いように感じます。そのあたりはどうですか?
たしかに、合理性を意識したこの運用方法に否定的な意見があるのもわかっています。
実際、矛盾を感じることのほうが多いくらいです。
たとえば職人の世界では、弟子が製品作りに携われるようになるまでに長い下積みがあります。それはなぜかというと、受け継がれるのは技術だけではないからです。
僕たちは人間です。忍耐力や精神力、仕事への誇りがないと長く続けることができる職人にはなり得ません。そういった文化を受け継ぐためには時間が必要なんです。
でもぼくたちにはもう時間がない。そのなかで、できることをやるしかない。
だからこそ、工場に迎え入れる人材は選びます。それはお互いに、ということですが。ぼくたちのビジョンを理解して、一緒にやってみようと本気で取り組んでくれる仲間がいることがありがたいですね。
矛盾を抱えながらも、一歩を踏み出さないことには問題は解決できません。
たとえ答えがないとしても

──お話を伺って、小林さんのモノづくりへの深い情熱を感じました。矛盾を感じながらも常に新たなチャレンジを続けていく原動力の源を教えてください。
ドライに聞こえるかもしれませんが、結局のところ問題解決が好きなんだと思います。
ぼくたちがやっていることには、ある意味正解がない。正解がないというか、パーフェクトがないんです。一つ答えを導き出しても、その答えが引き金になって次の問題が発生する。それが自然の摂理ですから。
それでも目指すところはわかっていて、そこに向かうために解決すべき問題があるからどうにかしたい。ここもまた矛盾していますが。
一つ明確に言えることは、職人が社会的地位を確立して、モノづくりを通して本当の意味で幸せに生きていける状態を、自分が生きているうちに作りたいということです。
──最後に。100年後、シーラカンス食堂がどういうカタチで存続していることが理想的だと考えますか?
火星か宇宙ステーションか。
どこか違う惑星で鍛冶屋をしてたら面白いですね(笑)。いや、火星はたとえばの話ですよ。
つまりどこであっても、100年後は100年後で、その時代に順応したモノづくりをして、継承している状態が望ましいということです。
時代に順応して変化しながら、本質的な部分をつないでいくことができるように。
それって、すごく楽しそうじゃないですか。
合同会社 シーラカンス食堂