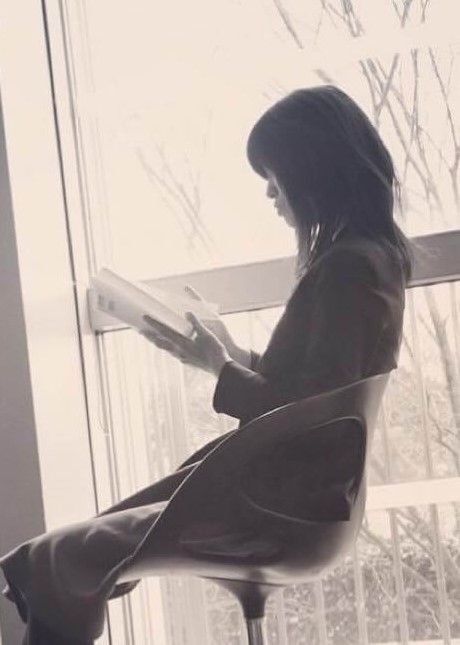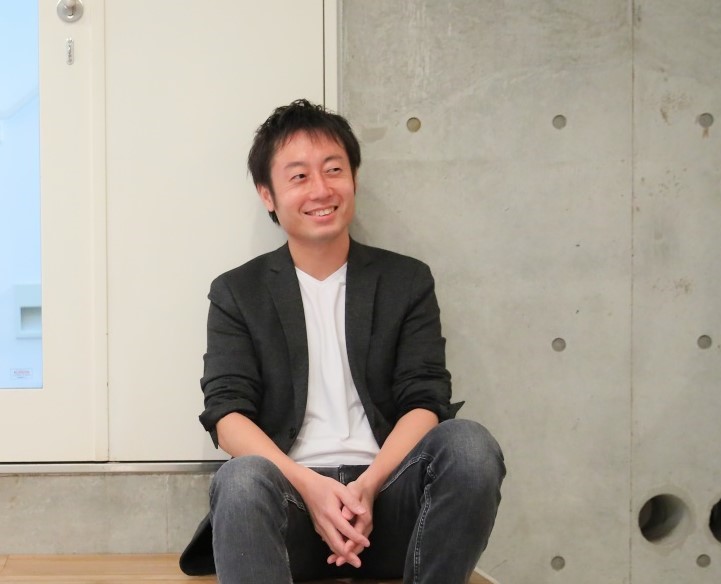Text by 紗矢香
写真提供:巧流合同会社
いつだったか、両親が赤いリボンの付いたスカートを履かせようとしていたのを、私は頑なに嫌がったことがある。私が気に入っていたのは黒と灰色のチェックのワンピース。かわいいモノよりもシンプルなデザインが好きだった。
当時は怒ることで自己主張をしていた。「これがいい」と思っているものとは別のものを与えられると「こっちの方がいいよ」と押し付けられている気がしていたのだ。
単なるイヤイヤ期と言ってしまえばそれまでだが、人は自己主張がうまくできない幼い頃からちゃんと自分の意志を持っていて、いいと思うものを選び取って生きているのだと思う。
けれど自己主張が強めだった私も、大人になると自分の意見や考えを通すことよりも「周りとの調和」を大切にするようになった。学校でも会社でも、周りと同じであることが当たり前のように思えていた。
ただ、人の目を気にするあまり「これがいい!」ではなく、浮かぬよう、目立たぬよう「無難であるか?」がいつの間にか服装選びの判断基準になっていたのは、ちょっと悲しかったりもする。
それでも、私の中でこだわりが完全に消えてしまったわけではない。
プライベートでは気分が明るくなるような真っ赤な服を着たり、虹色の縦縞がお気に入りの財布を眺めたりして、好きなものやいいと感じるものを何気なく日常に取り入れている。
主張は遠慮なくしたいし、調和を取りながらその場の空気にも馴染みたい。行ったり来たりを繰り返しながら、私のファッションセンスは少々いびつなかたちになってしまったようだ。
でもそれが案外、楽しい。
自己表現とは何か、調和とは何かを考えなら、自分の個性を磨いているような感覚になるからだ。
外を歩けばいろんな服装の人が歩いていて、個性は彩り豊かだ。そのなかでも「いまからどこへ出かけるのだろう?」と想像をかきたてられる装いがある。
着物姿の人だ。
街で見かけるとき、いつも自然と目が向いた。
*
ニットやパーカーの上に着物を羽織ってインタビューに臨んでくださったお二人。
洋服と和服を組み合わせた着こなしは、カジュアルでもあり、フォーマルでもあるたたずまい。街ですれ違っていれば、思わず振り返っていただろう。
兄の巧大さん、弟の誠也さんで立ち上げたブランド「巧流-call-」のホームページとInstagram には “新しい着物のかたち” が並んでいる。

着物とブーツを組み合わせたコーディネート、都会の街並みに着物姿のお二人。帯とベルトの巻き方一つで、伝統ある着物は、現代のスタイルに様変わりしている。
巧大さんが「着物は目立つけど、悪目立ちしない。いい意味で人目を引く」とおっしゃっていたのが印象的だった。私にとって着物姿は、自己表現と調和を両立した姿のように思えたからだ。
「ちょっと特別な日におしゃれしたい」
そんな希望を叶えてくれる「新しい着物のかたち」は、日常に溶け込みつつも、非日常を与えてくれるかたちを表現している。
この洗練されたブランドの誕生は、その華やかさとは裏腹に、業界の深刻な状況が関係しているのだという。
着物を仕立てる和裁の家系で生まれたお二人。もともとは、兄の巧大さんが父親の後を継ぐために国家資格である2級和裁技能士を取得し、弟の誠也さんは美容師の道を進んでいた。
ところが祖父の代から続く九州で4校あった和裁学院は、全て閉校してしまう。その後、父親と巧大さんで和裁の会社を立ち上げたものの、和裁業界はますます厳しくなる一方だったそうだ。
巧大さんは一度業界から離れて、カーディーラーの営業マンへ転身した。将来を案じた父親は言った。「もう戻ってくるな」と。
その状況を知った誠也さんは、兄の巧大さんに起業を提案する。
「祖父の代から業界を牽引してきた元山家が和裁業界を退くことは、着物文化の衰退にもつながる」
「若い世代がイノベーションを起こして、和裁士の持続可能性を高める使命があるんじゃないか」
「僕も美容師を辞めるから、一緒に会社を立ち上げよう」
そして2019年2月。
メインプロダクトである「約1分以内で着れる着崩れを起こさない “オーダーメイドの着物”」が完成。巧流合同会社は設立される。
掲げられた企業理念「粋ったDesignの”衣食住”」にはこんな想いが込められているという。
“今の時代にはなんでも揃い、物理的な争いは少なく、毎日ご飯も食べれる。そんな豊かな時代に生まれたこの”ラグジュアリーな時代(※)“なんだから、もっと笑顔を増やしたいじゃないですか。一人ひとりが”粋”を求め、上を向いて歩く。そんな世の中を創っていきたいです。”
note 着物テーラー 元山誠也より
(※人が生きていく上で最低限の衣食住が揃った、その先に生まれる、“必要性”のこと)
必要最低限の衣食住がそろった先に生まれる「必要性」とは何だろう?
私は「着たい服を選べる自由」を楽しむことがその一つだと思った。ファッションを自由に、心から楽しむ人が街中にあふれるイメージをすると気持ちが華やいでくる。
洋服と一緒にお気に入りの「着物」が一着、クローゼットの中に並んでいるとしたら。
その人の暮らしは、どんなに心豊かなものになっているだろう。

和裁士とつくる「生まれ変わり続ける着物」
──お二人が今日お召しになられているのはお店のものですよね。とても素敵です。「巧流-call-」さんは新しい着物のかたちを提案されていますが、着物に定義はあるのですか?
誠也:厳密な定義は存在しないんです。文字通り、着る物が「着物」だったので。
700年代に「右襟を前にして、左襟を上に重ねて着ること」という法律が定められたのですが、着物の定義はこれが唯一なんです。
ただ僕たちは、新しい着物のかたちを発信しているので、定義も当然必要だと思っていて。そこで「“和裁士”が仕立てたもの」を僕たちの掲げる着物の定義にしました。
生地によって縮み方が変わるので、特性を理解した上で、生地に合った仕立てができる。そんな職人の技術があってこそ、着物の新しいかたちを作り続けていけると考えています。
巧大:和裁士とは「生地と相談しながら仕立てる、生地に優しい職人」と僕は表現しています。そんな和裁士と作ったものは、今とかたちが全然違っていても着物だと思うんですよね。
誠也:あと和裁士が仕立てる着物は「直線の裁断」が特徴です。曲線で裁断しないことで、糸をほどいたときに着物が一つの長い布に戻り、コートなどへ新たに仕立て直すことができます。
長くかたちを変えて使うことができるところは、着物文化として残していきたい部分です。
──こだわりの技術を大切にされているのですね。ところで「巧流-call-」さんのお仕事は、同業の方にはどのように映っているのでしょうか?
巧大:父が経営する会社に外注をする際、そこで働く僕の兄弟子たちからは「こんな面倒なことをよくやるね(笑)」と言われることもあります。
僕たちが作るものは、今までにない特殊なかたちなので。

両衿先に紐がついています。紐を背中の穴通して着ることで、着崩れが起きにくく簡単に着ることができます。このデザインは意匠権という特許を取得しています。(写真提供:巧流合同会社)

洋服生地で着物を仕立てているので、保管やお手入れが楽です。洋服と組み合わせて着こなせるのでコーディネートが自由。(写真提供:巧流合同会社)
巧大:だからといって「できない」と拒絶されるのではなく「やってみよう」と一緒に考えてくれるんです。懸念があったとすれば、伝統的な着物業界で、新しいやり方を受け入れてもらえるだろうか、という点でした。
ただ僕たちは和裁士の家系で生まれ育ち、特に僕は職人の経験もあるので「この兄弟は着物の歴史を知った上で、ちょっと変わったことをやっているんだね」と認識してくださっているようです。
僕たちの周りの方々は、応援してくださる方たちばかりなので、嬉しいですね。
職人こだわりの着物で、日常はもっと自由に遊べる
──「巧流-call-」というブランド名を付けられた背景には、どのような想いが込められているのですか?
誠也:和裁士の持続可能性を高めるためには、技を磨くことのほかにも、技を伝える場所や伝えられる人、着物に惚れ込むファンの存在が必要です。
そういった方たちとつながるには、心の温かさであったり、対面での人との関わりが大切になってきます。
「和裁」の括りだけでなく、人の衣食住、暮らしが関係してくると考えているので、ブランド名の「巧流-call-」には「巧の技や知恵で世の中を大きく変える流れをつくりたい」という想いを込めました。
そして、想いをかたちにするために「愛着を創出し、社会問題解決への貢献」という使命を掲げています。
たとえばアパレル業界は、発展途上国の低賃金労働や、環境汚染につながる生産方法の問題と向き合っていますが、その要因の一つには「大量生産」があります。
大量に作られた手軽で安いものは、必要でなくても買ってしまう場合がある。買っても必要ではなかったからとすぐに捨て、捨てたからまた安いものを買ってしまう。
このサイクルが当たり前になってしまったことで「愛着」が失われたのではと考えています。
作る段階から職人が魂と愛情を込め、売り手も職人の愛情を消費者に伝えていく。消費者もそれを理解した上で購入すれば、モノへの「愛着」が生まれます。
愛着があるからこそ大切に、長く使っていく。
そのように「愛で循環する社会」を実現することが、根本の問題解決になると考えています。
着物というプロダクトを通して活動していくうちに、環境問題や社会問題への意識が高い方とお話をする機会も増えました。その方々との会話を踏まえても「愛着」が社会に必要だと感じています。
──着物の枠を超えて、社会や人々の暮らしまでを見据えた活動をされているのですね。日常に着物を取り入れたことによって、ご自身やお客様にはどのような変化がありましたか?
巧大:着物はいい意味で人目を引きます。悪目立ちしないんです。僕はもともと目立ちたがり屋で人前に出るのが好きなので、それも含めて着物を日常使いしています。
コロナ禍以前は着物姿で色々なところへ外出していて、そのたびによく話しかけてもらえました。一度お会いしただけですぐに顔と名前も覚えてもらえます。
そこから仲良くなって新しい友人ができたり、仕事につながったりして、とても人生の幅が広がりました。
お客様の例では、セルフブランディングを意識されている経営者やフリーランスの方が、大事な商談など「ここぞ」という場面で着てくださっています。着物が個性を際立たせるんですね。
また、落ち着きがあって上品さも兼ね備えているので「着物を着ることで発する言葉に厚みが出た」とおっしゃる方もいました。
将来的には、気軽に日常着として着物を着てもらいたい。僕たちが目指すのはそんな世界です。
……でも、いますぐには難しいと思っています。
なのでその一つ手前として、パーティー衣装やスーツの代わり、おしゃれをしたい特別な日などに、着物を選んでいただけたら嬉しいですね。

誠也:お客様の変化といえば、着物を通してご自身の新たな一面に気づかれることも非常に多いです。「着物文化がある日本に生まれて良かった」という感情が湧き上がるのだと思います。
アイデンティティが呼び覚まされるというか。その瞬間に立ち会えたとき、僕はこの仕事にやりがいを感じます。
ちょっと話は変わりますが「服用」という言葉の語源をご存じですか?
諸説ありますが、薬にも劣らない変化を、服は心と体に与えるものと見なされたことが始まりだそうです。服には自分の感情や想いを込められる。だからこそ、こだわって大切にしたいですね。
遊びを生む兄、仕組み化する弟。巧流-call-のこれから
──ご兄弟での共同経営ですが、役割分担はございますか?
巧大:僕は楽しいことをやりたい人。まず自分が楽しくないと周りも楽しくならないし、楽しめないと「世界」にいい影響も与えられないと思うんです。
もちろん仕事としてやっていくには、経済が回る仕組みが必要。そこは弟が「やりたいことをやれる仕組み」を作ってくれています。
誠也:兄の役割を一言で表すと「遊ぶこと」です。そして、兄が思いついた新しい遊びやアイデアを、僕がビジネスとして仕組みに落とし込みます。
僕は美容師をやっていたので、先輩の技術をみて自分の中に取り込み、習得しました。
物事の本質を捉えてかたちにするトレーニングをしていたことを考えると「巧流-call-」を立ち上げる前から、体系化して考えをまとめることは得意だったかもしれませんね。
──今後「巧流-call-」ではどんな“遊び”を予定されていますか? 今後の展望についてお聞きしたいです。
誠也:直近の目標は「和裁学院」を設立することです。そのためには、和裁士になりたい人を増やさないといけません。着物を着る人が増えて、和裁士の仕事が増える。これが一番にやることだと考えています。
そのため「和裁学院」を設立する前に、今後の活動のベースとなる「着物を着るのが当たり前の文化」を作ることに力を入れていきます。
文化とは日常で意識するものではなく、気づいたらそこにあるのもの。
その文化を作るには「こんなところで着物を着れたらいいな」という気持ちになってもらえる、非日常的でワクワクする和の空間の設計が重要だと思います。
そこで一つの手段として、近々barのオープンを予定しています。

長期的な展望としては、お客様の “すべてのニーズ” に合わせたブランド作りを考えています。着物は高価なイメージがあると思いますが、所得に関係なく、着物を着たいと言ってくださる方に僕たちは着物を届けたいんです。
リサイクルショップで売っている着物を使って、自分で仕立てられるようにする教室を開くなど、やれることはどんどんやっていきます。
お客様のニーズにお応えできるよう、一つの事業に捉われない広い視野で展開していきたいですね。
──最後の質問です。100年後「着物を着ることが当たり前の文化」になったとしたら、人々の生活はどのように変化していると思いますか。
誠也:「100年後のことはわからない」というのが僕の意見です。100年前の人がiPhoneを想像できなかったのと同じように、僕も100年後を想像できない。でも、誰かが何かを目指して作られた世界の先に100年後があると思っていて。
だから未来のことはわからないけれど、やりたいことを「どうやって実現させるのか?」はこれからも考えていきたいですね。
僕たちが大事にしていきたい「職人の想い」や「対面で人とつながりあう価値」を伝えられる場所が、100年後も存在することを願って頑張っていきたいです。