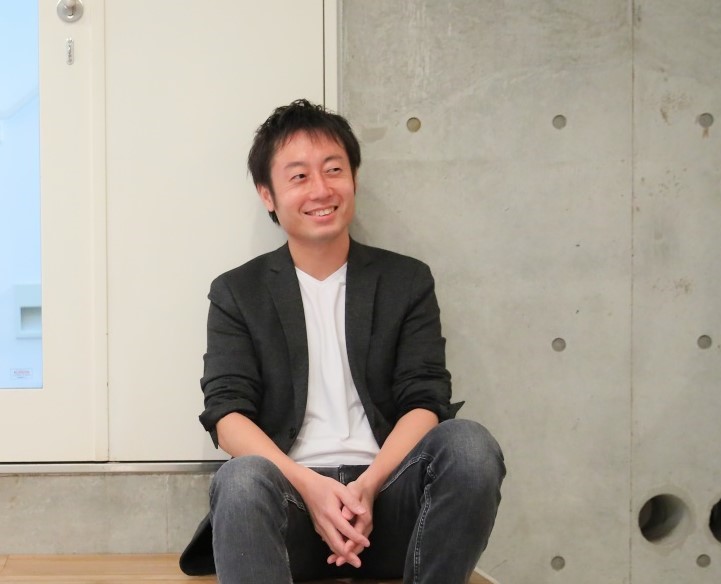写真提供:田中蒲鉾店
Text by 田中佳苗
旅先でおいしいものに出会うと、大切な人を思い出して「あの人に渡そう」とお土産にすることが多い。
自分が食べて感動したものを、相手にも共有したいと思うからだ。
人は本当においしいものを食べると唸る、そして笑顔になる。
どんなに落ち込んでいたとしても、すっかり忘れて幸せになっていたりする。
それだけ、おいしい食べ物は誰にとってもエネルギーになっているのだ。
米どころ新潟に生まれながら、一人暮らしを始めたころは、手軽で安いからとチンするご飯をよく食べていて、正直お米の味を気にしたことがなかった。
社会人になったあるとき、偶然知り合った農家さんから買ったお米を、せっかくだからと土鍋で炊いて食べた。あまりのおいしさに感動したことをよく覚えている。
新潟といえばお米、和歌山といえばみかんのように、その地域を代表する食材もたくさんある。
食べ物は時に、地域の魅力を伝えてくれるし、おいしさの感動と笑顔を届けてくれる。
*
地域食材を使いながら、地域のことも伝えていきたいと奮闘している生産者はたくさんいるのではないだろうか。
鹿児島県姶良市(あいらし)で約80年続く、老舗蒲鉾店三代目の田中健太さんもその一人だ。
創業当時から変わらない「ごまかしの効かないおいしさ」を守りながら、時代とともに変化した商品展開を進めている。
同店は、甘いさつま揚げを多く生産している県内では珍しく、甘くないさつま揚げを販売。
コロナ禍の中、季節の食材を使用した新商品は2ヶ月に1回販売し、地元高校生とのコラボ商品開発にも取り組んでいる。
そのほか、健康や安全を意識している現代人のニーズに合った「無添加さつま揚げ」は、2019年に鹿児島の新特産品コンクールで奨励賞を受賞。
「SNSの発信をはじめたけど、更新するだけで精一杯で…」と言いながらも、SNSの写真はどれも綺麗で、なかには見やすくPRデザインされている商品まである。
さつま揚げと聞くと、正直どうやって食べたらいいのかわからないという人も多いと思うが、そんな需要にも応えてた「さつま揚げを使ったレシピ」なども紹介している。
若い人向けにはチーズハットグ風の「チーズハットギョ」や、さつま揚げのすり身で作ったコロッケ(魚ギョロッケ)など、バラエティに富んだ商品も販売。
田中さん自身は控えめに話しているが、その取り組みや、実行していることはどれも並大抵のことではないと思う。
その発想力や実現する力はどこからきているのだろう。どんなことを考え、さつま揚げと蒲鉾店の未来を見ているのだろう?
受け継がれてきた「ごまかしのきかない美味しさ」ブラジルの経験をさつま揚げに
──小学生がよく「将来の夢」を作文で書きますよね。私は当時、母の作る焼き菓子が大好きだったので、ケーキ屋さんになりたいと書いていました。田中さんは、小さい頃から蒲鉾店を継ごうと思っていたのですか?
はい。そうですね。
田中蒲鉾店は、もともと魚屋を営んでいた祖父が、余った魚を活かすために蒲鉾を作り、販売したことが始まりでした。
お歳暮などの贈り物として利用していただくお客さまが多く、繁忙期の年末は1週間ほど泊まり込みで発送作業をします。
子どもの頃から、兄と一緒によくお店の手伝いをしていました。
当時からお店を継ぐのは兄ではなく自分ではと感じることが多く、小学校の作文で書く「将来の夢」は決まって同じでした。
「ぼくは、大きくなったら蒲鉾店を継ぎます!」
いま思うと、三代目と書くと友達の反応が面白かったからかもしれません。

──きっとお父様も喜ばれていたでしょうね。学校卒業後すぐに田中蒲鉾店に入られたのですか?
いえ、大学卒業後、数年経ったあとに入りました。
二代目の父親も蒲鉾とはまったく関係のない勉強をしてから事業を継いだので、私も何か違うものを勉強しようと思い、外国語大学に進学しました。
大学3年生の時に約1年間ブラジルへ留学し、大学卒業後もアルバイトしながらお金を貯めてはブラジルに行っていました。
──何度もブラジルに行かれているんですね。なぜブラジルに留学したのですか?
ポルトガル語で話す国に行こうと探していたら、ブラジルかポルトガルの二択でした。
当時スケボーをしていたので、より盛んな国に行こうとブラジルを選びました。ブラジルに行ってから国技であるカポエイラに出会い、かれこれ15年以上続けていますね。
カポエイラは、格闘技と音楽、ダンスの要素が組み合わさったブラジルの伝統文化です。
今ではすっかりカポエイラにはまり、お店の2階スペースを開放してカポエイラ教室もおこなっています。
──カポエイラ教室は、田中さん自身も楽しく続けながら、ブラジルの伝統文化を広めていますね。伝統というところで、さつま揚げ作りと共通する部分はありますか?
どちらもこれまで昔から伝えられてきたものなので、それを残していきたい想いは共通しています。
そのためにもこれまでのことを伝えつつ、新たなものも発信していくことも必要だと思っています。
さつま揚げは、新しい味や食べ方も提案していきたいと考えていて、SNSでもさつま揚げレシピを発信しています。

──現在事業継承されてから2年目とのことですが、田中さん自身が大切にしていることはありますか?
創業当時から水、塩、糖などの原料にこだわり「ごまかしのないおいしさ」を大切につくり続けています。
お店として守り続けてきたことを、私も大切にしています。
鹿児島のさつま揚げは甘い味付けが一般的ですが、田中蒲鉾店は「甘くない」のが特徴です。
全国の催事場に出店するときも「鹿児島産ですが甘くないんですよ」とお伝えすると、意外そうな顔で試食してくださるんです。
そして決まって「おいしい!」と驚いてくれる。
それが嬉しいからこそ、この味を守り続けているのかもしれません。
さつま揚げをアップデート。地域の人と作り上げていくコラボ商品
──昨年販売された「無添加さつま揚げ」は他にはない珍しい商品だと思います。無添加で商品を作ることはなかなか大変なことだと思うのですが、なぜ商品化しようと思ったのですか?
祖父が創業当時から「塩だけでさつま揚げをつくりたい」という想いがあったようで、その話を聞いてから、なんとか形にできないだろうかと考えていました。
通常のさつま揚げには澱粉、卵白、砂糖のほか調味料を入れています。無添加さつま揚げは、それらを一切使わず、原料は魚、油、酒、塩のみです。
同じ地域で無添加ソーセージを作っている方に協力していただきながら、約2年かけて完成させました。
原料もシンプルなので、魚本来の旨味が味わえる一品になっています。
魚は近海でとれた魚だけ、酒は鹿児島の黒酒を使用しています。
また、塩は岩塩などをブレンドし、揚げ油には玄米の栄養をまるごと吸収できるこめ油など、素材にもより一層こだわりました。

──先代の想いを田中さんが実現しているんですね!
無添加商品の生産には課題がたくさんありますが、解決手段の一つとして真空パックを活用しました。
ほかにも、包装の工夫により商品化が実現したものもあります。「らっきょうさつま揚げ」です。
15年以上前に一度は商品化されたものの、らっきょうの香りがほかのさつま揚げにうつってしまうという理由から生産を中止していたそうなんです。
当時の様子を聞くと味も好評で人気商品だったとのこと。そこで、今だからできる個包装を導入し、商品化に踏み切りました。
昔販売していたことを覚えていてくれたお客様もいて、懐かしいと購入してくれます。
──田中蒲鉾店さんでは、若い人も好むようなバラエティに富んだ商品がありますね。なかでもチーズハットグ風の「チーズハットギョ」が気になりました。
「チーズハットギョ」は夏の花火大会でも販売しました。
若い方はさつま揚げに馴染みがないと思うので、中身を変える以外にも色々な形のさつま揚げを販売しています。
たとえば、
- 魚嫌いのお子さんのために作ったチーズ入りのさつま揚げ
- すり身で作ったコロッケ
などがあります。
現在もさまざまな商品開発に挑戦中です。

さつま揚げのイメージを変えながら、若い人にも身近な食べ物になったらいいなと。
今年から地元高校生と一緒に商品開発をしているので、そういった取り組みからも若い人がさつま揚げのことを知るきっかけになっています。
──地元高校生とのコラボも新しい商品が生まれそうですね。
そうですね。特産品協会で知り合った食育日本料理家の梛木さんから声をかけていただき、今回コラボさせていただきました。
高校生も自分たちで試作しながら進めていたのですが、斬新な発想に驚かされました。
試作段階でドラゴンフルーツも入れてみたと聞いて、そんなのもありなのかと思いました。「自分ももっといろんな食材を試さないと!」と感じましたね。
試作を繰り返すなかでいくつか提案してもらったのですが、その一つに「トマト入りさつま揚げ」がありました。
トマトを入れることも考えたことがなかったので、どんな味になるんだろうとお店でも作ってみたんです。そしたら、意外とスッキリした味になっていておいしかったです。
本来は、販路拡大や地域鹿児島のPRのため、今年開催される予定だった鹿児島国体で販売予定でした。
しかし、コロナウィルスの影響で国体が中止になり、販売の企画もキャンセルになってしまいました。
現在は、他の販路探しをしているところだそうです。どうやって販売するかもとても勉強になりますし、販売が楽しみですね。
トマトさつま揚げとは別に、コラボ商品のさつま揚げの材料を高校生が探してきてくれたこともありました。
──材料を探すというのは、生産者を見つけるということですか?
野菜を生産するときに、どうしても規格外のものはでますよね。
今回だと、種子島で生産されている安納芋でした。
普段は小さくて販売できないそうなんですが、さつま揚げに入れる具材は小さく刻んでしまうので、大きさは関係ありません。
お店としても地域の食材を使うことができ、生産者としても規格外商品を破棄はせずに販売することができます。
こうした取り組みはフードロスにも、地域のつながりにも貢献できるよい機会になりました。
高校生が、生産者と製造者の地域のつながりを考えてくれることも嬉しいことです。
―─いろんな人が商品開発に関わることで、新しい商品や発想が生まれていきますね。ほかにコラボしている商品はありますか?
きくらげを生産している同級生に「さつま揚げに入れてみてよ」といわれて、試しに作ってみたらおいしかったので商品化しました。
特に今年は季節の商品を少しずつ増やしてきました。色々な食材を試しながら、2ヶ月に一度くらいのペースで商品化してきました。
加工業だからこそ、さまざまな地域の食材を使うことができるので、さつま揚げを通して鹿児島のことを知ってもらえるようになったら嬉しいですね。
県内産だけにこだわっているわけではないのですが、県内にもまだまだ試してみたい食材がたくさんあります。今後もコラボ商品開発はチャレンジし続けていきたいと思っています。
伝えたくなる美味しいさつま揚げを目指して
──積極的に商品開発をしている姿が周りの人にも伝わっていて、「協力してほしい」という声が多いと思いました。田中さん自身が今後取り組みたいことはありますか?
まずは「鹿児島のさつま揚げは甘い」というイメージを変えていきたいと思っています。
歴史的背景から鹿児島のさつま揚げは甘くなったといわれています。ですが、もともと砂糖は高級食材だったので、本来最初に庶民が食べていたさつま揚げは甘くなくて、もっとシンプルだったと思います。
また、さつま揚げはお歳暮や引き出物に使われることが多いので、特別食と思われがちですが、もっと日常でも食べてもらえるようにしていきたいです。

──日常食としては、どうしても大量生産の商品と比較されてしまうこともありますよね。
近所のスーパーにもさつま揚げを卸しているので、工場生産の商品と比べると量や値段では勝てないなと感じます。
それでも田中蒲鉾店の商品を選んでもらえるよう、品質はもちろん、こだわりをPRできるよう努力しています。
いまは既存のお客様へのDMが中心です。新商品が出る度にDMを送っていて、そこからご購入いただくことが多いですね。
あとは、お歳暮などの贈り物で商品を食べた方が、「おいしかったから」とリピーターにつながっています。
──一度食べるとおいしさがわかり、また食べたくなるさつま揚げになっているからですね。
そうですね。商品の品質や味を知っていただき、再度購入いただけるのはとても嬉しいです。
しかし、私も含めて、今の若い方はお歳暮やお中元を贈ることが少なくなってきていると思います。
そうなると、さつま揚げを食べる機会も、知る機会もなくなってしまうので、ネットやSNSでの発信もしています。
SNSが得意なわけではありませんが、まずは情報を発信することをしっかりして、こだわっている部分がPRできるように活用していきたいです。
──最後に、これからの続いていく田中蒲鉾店のどんな未来を想像していますか?
事業継承でいうと、子どもたちに必ず継いでほしいとは考えていません。
まずは、今目の前にあることを一つひとつ取り組んでいくことが大事だと思っています。
留学の縁から、ブラジルでの販売の話もありました。海外販売となると、クリアしなければならない課題がたくさんありますが、今後の目標として実現できたらいいなと。
全国から世界へ、田中蒲鉾店のさつま揚げが飛び立ったら面白いですね。
同時に、さつま揚げの魅力も伝え続けていきたいです。
さつま揚げを広めていくことで、鹿児島や姶良市のことを知ってもらうきっかけになったらいいなと思います。
認知され、魅力が伝われば、自然とお店を構える地域にもいろんな人が来てくれるようになるのではないかなと。
長く続けた先に、子どもたちが自分の意思で継ぎたいと思ってくれたら、とても嬉しいです。
父に対して自分がそうであったように、日常にあるおいしいさつま揚げを繋いでいきたいと思ってもらえるような、さつま揚げつくりをこれからもしていきたいです。
人はおいしいものを食べると感動し、それを大切な人に伝えたいと思います。
その伝えたくなるおいしいものが「田中蒲鉾店のさつま揚げ」だと選んでもらえるように、これからも挑戦し続け、新たな感動を生み出せる蒲鉾店を目指していきたいです。
有限会社 田中かまぼこ店