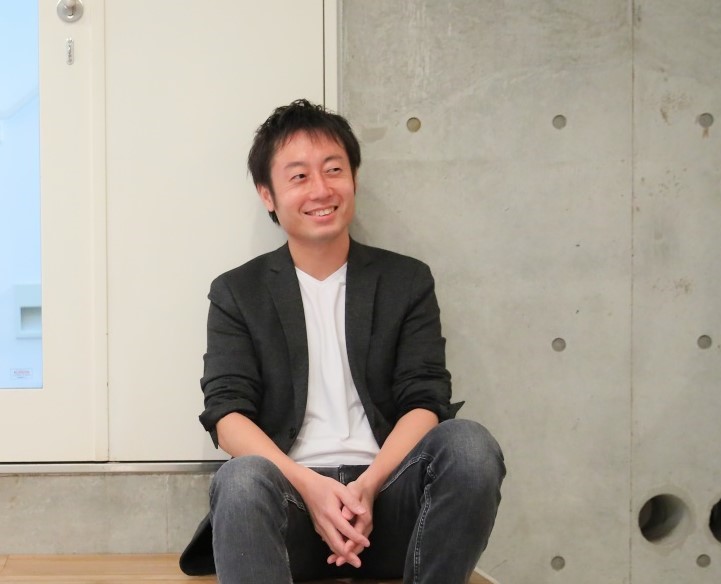写真提供:田村七宝工芸
Text by 大崎博之
子どもの頃、「将来の夢」というテーマで作文を書くのが苦手だった。
パン屋さんになりたい、お花屋さんになりたい。同級生たちがそれぞれのテーマで未来を描くなか、私はただ、大人になる自分を想像できないでいた。
高校生になると「いつかコンビニの店員になりたい」と大真面目に宣言していた。1997年の田舎町におけるそれは、憧れの象徴だった。
……というのはウソ。
どれだけ年を重ねても、私は大人になりたくなかった。社会になんて出たくなかった。
いつから自分にとっての世界は、無色なのかモノクロなのかもわからないほど色褪せてしまっていたのか。
一方でその頃、まさしく同時期に、私とは正反対の価値観を持つ女の子が、愛知県の七宝町で暮らしていた。
「私も、将来の夢が書けないんです。なりたいものが多すぎて!」
*
時は経ち、2019年。あの日のことは鮮明に覚えている。
「社会で活躍できる女性」の発掘を目的とする、とあるビューティーコンテスト。
その会場に「和」の衣装で登場した彼女は、生まれ育った町の伝統工芸、七宝焼(尾張七宝)が存続の危機にあることを伝えていた。
「約200軒あった窯元は、現在わずか8軒。跡継ぎはもう、私しかいません」
あまりに衝撃的な内容。
そして同時に、自らを「先駆者」と表現する彼女がこれまでに挑戦してきた数々の取り組みに心が震えた。驚くという感情表現ではとても表しきれなかった。
作品を拝見し、その美しさにも圧倒された。
特に私の心を捉えたのは『七宝ペンダント 輝く日の宮モデル 其の五』と題された作品。
話を聞けば、徳川美術館にて行われたグループ展でお披露目した「源氏源氏物語絵巻」とのコラボレーションだという。

最近では人気キャラクターとのコラボレーションやゴルフマーカーなど、七宝焼の既成概念を超えた取り組みが注目されている。
しかも彼女の凄いところは、自らの「職人」という枠すらも飛び越えているところ。
大学時代には芸能事務所に所属し、年間200本のライブをおこなう歌手として活躍。2020年にリリースされた七宝焼職人のテーマソング「熱量のアイリス」は、NHKの全国放送で紹介されるまで話題を呼んだ。
ブランディングや広報活動に強みを持つ彼女の勢いは、ますます加速するばかりだ。
一方で不思議に感じることもある。
彼女がそこまでするのは、本当に伝統を守りたいという想いからだけなのだろうか。彼女が七宝焼を通して届けたい「ほんとうのこと」は何なのだろう。
もっと、もっと話を聞いてみたいと思うようになっていた。
七宝焼の世界にブランディングを
──ご無沙汰しております。実は以前にも別の機会で取材させてもらっていて、今回で2回目なんですよね。改めて、現在の活動をするようになった背景を、自己紹介も兼ねて教えてもらえますか?
またこうして機会をいただけて嬉しいです。あ、自己紹介ですね。
私は日本の伝統工芸、七宝焼(尾張七宝)の職人をしています。「明治16年創業七宝焼の窯元、田村七宝工芸のゴダイメです」とお答えすることが多いです。
小さな頃から両親やおじいちゃんの作る七宝焼の作品が大好きで、自慢で、いつもカッコイイな~って感じながら過ごしてきました。
ただ、世の中の人が見る機会があまりに少なかった。だからこそ「みんなに見てもらいたい!」という想いが強くなりました。
「ゴダイメ」と片仮名で名乗っているのは、四代目当主の父がまだ現役だからです。「五代目」と言ってしまうと、なんだか父が引退しているように聞こえてしまうので。

──経歴を見ると、大学卒業後すぐに現在のお仕事を始めてはいないんですよね。なぜでしょうか?
両親から「継いでほしい」と言われたこともなかったですし、私自身も初めは跡継ぎになることを考えていなかったんです。猫の手も借りたいほど忙しい状況であれば考えなくもなかったのですが、実際はそうではありませんでした。
仮に継ぐ意思があったとしても、そのときにはできなかった理由が2つあります。
1つめは、やみくもに継ぐことはリスキーだと感じていたからです。
黙っていても仕事があった昔とはちがい、作れば売れるという時代ではありません。何の考えもなしに後を継いでも将来性がないと考えていました。
2つめは「私がやらなければいけない理由」を私自身が見出せなかったからです。
父だけでなく母も現役で七宝工芸に従事していたので、私があえて七宝焼をする理由もないというか……。私だからできる何かが必要だと感じていました。
──実際は大学卒業後に何をされていたのですか?
企業に就職し、Web制作や撮影ディレクション、イベント、舞台製作など、さまざまなことを経験させていただきました。
それらのお仕事を通じて、自分だからこそできることに気づいたんです。七宝焼の世界に「ブランディング」を持ち込むことができるのではないかと。
モノや情報があふれる時代に、正しく魅力を伝えられる力はとても重要です。そこでまずはWebサイトを作り、ロゴやシール、パッケージも用意しました。メディアで紹介されやすい切り口も考えましたね。
最初の企画はこうです。
「1883年より続く七宝焼の窯元で、五代目の娘が七宝ジュエリーブランドを立ち上げ!」
──とてもキャッチーな企画ですね。私も取材したくなりました(笑)
ただスタンスとして、何年も先の事業計画までは立てていません。まだそこまでできる段階ではなかったので。そうではなく、目の前の一つひとつの小さなキッカケを大切にしています。
その結果、人気キャラクターの『スヌーピー』とのコラボレーションが生まれたり、東海3県若手女性職人グループ『凛九』の発足、中小企業技術屋集団『KASANE CHUBU』の企画にも声をかけていただき、数々の作品をお届けすることができました。



宝飾工芸「七宝焼」が成す意味を考える
──次々と斬新なアイデアを打ち出す田村さんですが、その発想源は何なのでしょうか?
とにかく色々なものを見るようにしています。まったく関係のないところから着想することが大事だと思っているからです。七宝焼の世界だけにいると、固定概念に頭のなかが縛られてしまうので。
たとえば、絵画や彫刻もそうですし、工芸とは縁遠く感じるAI関連のニュースなども見たりします。
そもそも伝統工芸も、発祥の頃は当時の「最先端」であったはずで、職人はいわば「先駆者」のような存在だと私は捉えています。
だからこそ古きを守りつつ攻める精神が大切だなと思っていて。最近は宝飾品でありながら「機能美」も備えたものを作れないかと考えています。いつか「七宝Tech(テック)」という言葉を生み出せたらおもしろいですよね。たとえばですが(笑)
──伝統を守りつつ、新しいものを生み出すバランス感がすごいです。
既存のものを作りながら、新しいことに挑戦していますね。
しかし、変わったものばかりを作っていると「七宝焼ってそもそも何だっけ?」ということになりかねません。
奇をてらうのではなく、目線を変える。これは私が本格的に制作活動を始めた2015年から言い続けていることです。
とはいえ、私が新しいことに挑戦できるのは、両親がしっかりとした作品、商品を作っている環境があるからです。


──少し抽象的ですが、田村さん自身は「七宝焼とは何か?」という問いに、どんな答えを現時点でお持ちなのですか?
形式的な回答をするなら「銀、銅などの金属にクリスタルガラスを焼き付ける、国の伝統工芸品です」と答えます。
ですが、その問いの本質的な解は当然ちがいます。
「宝飾品は、なくても生きていけるもの。それの成す意味は何か?」
ずっとそれを考え続けてきた結果、心の豊かさに辿り着きました。
栄養価の高いゼリー飲料だけを飲んでいれば食事はいらないのか。ほとんどの方は「NO」と答えるのではないでしょうか。人間は機能だけを求める存在ではないからです。
ロボット掃除機もまた、生活をラクに快適にさせますが、心を豊かにするものではないと思います。「機能のカタマリ」だけでは足りないんです。
人間を人間たらしめるのは、心の豊かさです。
私はそこに対して「七宝焼」が担える役割があると考えています。先ほど「機能美」の話をしましたが、機能だけを追ってしまっては、それはもう「七宝焼」ではないと思います。
伝統に根ざした、豊かな暮らしを届ける

──田村さんはお仕事を引き受ける際、どのような選択基準をお持ちですか?
直接的な答えではないですが「伝統とは何か?」を意識して注文をお受けしています。
伝統の定義は長く続いたもの、ではありません。私は「伝統とはアイデンティティである」と結論づけました。
長く続いてきた背景には、そこに息づいてきた暮らしや生活というものがあり、工芸の歴史や使われている素材などをトータルで見ることで「伝統」が輪郭を現します。
逆をいえば、経緯を汲むことをせず、今まであったことを疎かにすることは「アイデンティティの欠如」を意味するので、ご依頼をお断りしています。
大量発注、大量生産を仮に求められたとすると、私はそれをお受けできません。
私はWebでの発信やブランディングを大切にしていますが、何も考えずに目新しいことをやる、ということはしないようにしています。
──反対に、こういうご依頼だったら喜んでお受けします、というものはありますか?
自分が楽しいと感じるものは積極的にお引き受けしています。自分の心が躍るものであれば、その感覚はぜったいにお客様にも届くはず。
印象に残っているのは、お客様から「両親へのプレゼントがしたい」とご依頼があったときの制作です。新婚旅行の旅先で購入したチューリップの絵画があり、それを七宝焼の平面作品にしてほしい、というものでした。
絵のデザインを「七宝焼」のデザインとして抽出し、インスピレーションを大切にしながら作品へと仕上げました。

「こんなことができるんだ!」と、依頼者のお客様にもご両親からも喜んでいただけました。長文のメールでお礼の文章が送られてきて、すごく嬉しかったのを覚えています。
──伝統を大切にした上で、これから展開していきたい田村有紀流の七宝焼をどのように構想していますか?
武蔵野美術大学の造形学部「建築学科」を卒業していることもあり、建築やインテリアと掛け合わせたものができないかと構想を描いています。
建物や設備施設とのコラボレーションなのか、それともそこに置くものなのかはまだ明確ではありませんが、人生や生活の一部に七宝焼が存在できたらいいなと思っています。
建築は人が生きることにかかわるすべてを作る学問です。側(がわ)だけを作るのではなく、どう暮らしたいのか、どういった生活を営みたいのか、そこまでを考えて設計する必要があります。
七宝焼は長く日に当たっても色が褪せることなく、いつまでも変わらない美しさを保てる特徴があります。そのため、表札やブランドのネームパネルとして使われることも多いんです。

人が感じる「美しい」や「かわいい」といった感性はいつの時代も変わらない。
だからこそ、ワクワクや楽しいといった、人生を明るくするような豊かさを届けたい。日用品ではない「宝飾工芸」ならではの視点で七宝焼を伝えていきたいです。
田村有紀の考える「七宝焼」の未来
──この記事では伝統工芸の未来、具体的には後継者問題にも触れたいと考えているのですが、田村さんはそれについてお考えはありますか?
これまで私は自分にできる精一杯のことをやってきました。職人として楽しく生きる方法をたくさんの人に見ていただきたいと考えるからです。
一方、このままのロールモデルでは「私」がいないと成立しないものになるという危機感もあります。
実はすでに「七宝焼職人になりたいです」というご連絡をいただくこともあります。でも、お応えできないのが現実です。私には時間的な余裕もなければ、お給料を払えるような余裕もありません。
それに、継ぎたい人に対して「私のマネをして」と伝えても「イヤだ」と言われるのがオチです。その人にはその人のやりたいこと、やり方があるはずです。
だから私は「経営者」になりたいと、いまは考えています。
継ぎたいと言ってくれる方に対して、やりたいことができる環境を用意してあげる。ベスト解ではないですが、体験教室の開催などで固定収入が得ながら、作品づくりに集中できたらいいですよね。
人を雇えるようにしないかぎり、後継者は増えていかないと思います。
──雇用面を見越して、将来的にやりたいことはあるのですか?
私、工芸タウンを作りたいんです。
そこでは「金属を叩く日」みたいな、手を動かして遊べるイベントが開催されたりして。楽しいと思いませんか?(笑)
フリースクールのようなイメージというか、一過性ではないかたちで教育にも携わっていけたらと思い描いています。
小さな頃の私は「将来の夢」を作文で書けなかったんです。なりたいものが多すぎて。
だけど、やりたいことや夢を話せば話すほど、笑われちゃうんです。両親だけは自由な心を尊重してくれて応援してくれましたが、まわりは違った。
「みんな一緒が正しい」という価値観のなかで私はうまく生きられなくなってしまった。そういう経験もあって、教育をかけ合わせた活動もしたいんです。
それが町単位のものなのか、私の手が届く範疇のものかはわかりません。でもそこから新たな職人が生まれ、雇用が生まれ、工芸が好きな人が各地から集まったら…と考えるんです。
まだ何も成しえていなくてお恥ずかしいのですが、もしそれが実現すれば、私がいない100年後であっても経済がまわり、楽しんでいける「七宝焼」の新しい世界が生まれるんじゃないかなって。
そんな未来を想像しています。